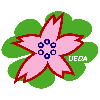第19回自主制作映画コンテスト 結果とコメント
うえだ城下町映画祭第19回自主制作映画コンテストは131作品の応募がありました。
審査員3名(大林千茱萸、柘植靖司、古厩智之)による審査の結果、ノミネート15作品が選出され、その中から大賞1作品、審査員賞3作品が決まりました。
また、全131作品を対象に実行委員会で行った審査で、実行委員会特別賞1作品も決定しました。
受賞作品
| 賞 | 作品名 | 監督 | 作品の 時間 |
|---|---|---|---|
| 大賞 | 「10年後の君へ」 | 榊 祐人 | 58分 |
| 審査員賞 (大林千茱萸賞) |
「Yokosuka1953」 | 木川 剛志 | 106分 |
| 審査員賞 (柘植靖司賞) |
「アクト」 | 田中 夢 | 74分 |
| 審査員賞 (古厩智之賞) |
「バンド」 | 河村 陸 | 28分 |
| 実行委員会特別賞 | 「Yokosuka1953」 | 木川 剛志 | 106分 |
ノミネート作品
| 作品名 | 監督 | 作品の 時間 |
|---|---|---|
| 「にしきたショパン」 | 竹本 祥乃 | 90分 |
| 「ライフライナーズ」 | 菅原 稜祐 | 38分 |
| 「平成居酒屋~月の光~」 | 上島 大和 | 35分 |
| 「夢見びと」 | ケンジョウ | 100分 |
| 「PARALLEL」 | 田中 大貴 | 84分 |
| 「青春の切れっ端たち」 | 森田 和樹 | 129分 |
| 「静かなる夜」 | 大村 諒 | 40分 |
| 「独゛dog」 | 岡上 亮輔 | 29分 |
| 「スタートライン」 | 藤井 謙 | 30分 |
| 「いつか大人になろうとも」 | 小寺 渚、中山 慧南、羽原 優衣、濱田 莉子 | 15分35秒 |
| 「冷めるのを待っている」 | 佐藤 杏子・岡本 香音 | 26分 |
審査員コメント
総評
このコロナ禍で制作を続け、完成させ、この映画祭に応募して頂いた制作関係者の皆さんに頭が下がります。感性予防に苦心され、もしかしたら撮影することに周りからは白い目を向けられたのでは、とも想像します。たぶん、世間では自主映画制作は『不要不急』と言われる範疇に入るかもしれません。それでもカメラを回さずにはいられない。皆さんのその思いは伝わってきました。
今回、受賞作品にドキュメンタリー作品が2本が選ばれました(どちらも撮影はコロナ禍以前に行われた作品のようでしたが)。コロナ禍を逆手にとった作品もありましたが、私の個人的な思いとしては「フィクション、もっと頑張れ!」という感じでした。制作される映画がその時代の鏡である部分があるとすれば、このコロナ禍を体験した影響が作品の中に現れてくるのには、少し時間が掛かるかもしれません(まさにまだコロナ禍最中ですから)。
うえだ城下町映画祭関係者の皆さんの最大限のご努力もあり、この映画祭は継続されました。『継続は力』です。皆さんの創作活動が途切れないことを、そして、来年は酒を酌み交わしながらの対面での歓談を心から願っています。(柘植靖司)
大賞「10年後の君へ」
冒頭、タクシーの後部から運転席側のドアーミラーに向かって、ゆっくりとした移動の
カットがあります。このカットのバックにはカー・ラジオからご機嫌な音楽が微かに聞こえています。このカットが秀逸でした。これからどういうドラマが始まるのか、見る者をまず引き付けます。次のカットで主人公のアップが映し出されるのですが…3分程のこの冒頭のシーンがこの映画のテンションとリズムを支配しています。少なくともこの映画を見始める私の期待を最後まで裏切らない冒頭シーンでした。
物語のテンポがとても軽やかで、少し驚かされるのですが、とても心地好い。何か暖かいものがじわじわと伝わってきました。
監督は応募書類の自己紹介に『映画を作るのも、観ることも好きです』と書かれていますが、この監督が映画を愛している素直な想いと生き方が全編に漂っています。母娘の「はるか」と「かなた」のネーミングをはじめ、監督の遊び心(?)が散りばめられていて、各所でニヤリとさせられました。娘「かなた」の成長の描き方が「かなた」の心のひだに触れるようでした。この女優さんのポテンシャルがこの役にジャストフィットしていたのでしょうか。病院で出会う少年も素晴らしいキャスティングでした。
『全ての芸術は模倣から始まる』と誰かが言っていましたが、模倣しても模倣しても決してオリジナルにはなり得ない…。そのオリジナルにならない部分にこそ、その作家のオリジナリティがある。そんなことをこの映画から感じさせてもらいました。
十年後の監督作品がとても観たい!(いや、次回作もですが…)。 (柘植靖司)
優しい母があっけなく死ぬ。あと少しで仲良くなりそうな男の子はふいに大阪へ行ってしまう。憎まれ口を叩いていた父は突然ガンに。入院患者の子どもも約束を果たせないまま死ぬ…。死別や別れが繰り返される。
あっけなく去っていく、または置き去りにされる俳優たちがみな魅力的!どの人物にもクセが、個性がある!不満や望み、いいところと悪いところがあって人間的。だから彼ら登場人物たちをすっかり好きになってしまう。
そして思う。彼らを好きになったのだから、必ず別れが待っている人生も、素晴らしいものなのではないか。
見ていくうちに自分の中で価値の転倒がおこっている。別れや死といった人生のネガティブな側面を、いつのまにか「それ込みで素晴らしいもの」として自分が受け止めていることに気付く。
人生はそれじたいが祝祭だ、と謳うクライマックスの歌と踊りのシーンでは、涙が出た。(古厩智之)
大林千茱萸賞「Yokosuka1953」
「木川信子を知っていますか?」――。『Yokosuka1953』は戦後の混乱期に生きていた、しかし歴史では語られることのない、誰にも語られず忘れ去られようとしていた女性・木川信子さんに焦点を当てたドキュメンタリー作品。そのはじまりが、まったくの偶然であることに、まず驚く。アメリカに住む木川信子さんの娘・バーバラさんが日本で生き別れた母を探すために、「木川」という名字だけを頼りに、同じ名字の日本人がいるから聞いてみようと家族の協力を得て木川剛志さんのFacebookに一通のメッセージ送ったことからだというのだ。
血縁でも何でもない木川剛志さんは最初、「何かお役に立つことができるなら」――くらいの気持ちだった。けれど木川剛志さんは大学の教授で、日本国際観光映像祭総合ディレクター。たまたま映像の専門家で、たまたま英語でのコミュニケーションに長けていた。結果、木川剛志さんはこの「偶然→たまたま→必然」で流れ込んできた強い縁(えにし)を請け負うことにする。記録の残っていない木川信子さんの過去を紐解くさまを、丸ごと映像作品にすることを決める。覚悟を決め、果敢に取材し、何本もの細い糸をたぐるようにして映像を撮り重ね、記録し直してゆく。
映画の縦糸となるのは木川信子さんの歴史だが、作品に織り込まれる横糸としてのバーバラさんの存在と行動、その強く揺るがない想いに圧倒される。バーバラさんは木川信子さんの娘さん。日本人の母と外国人の父の間に横須賀で生まれ洋子と名付けられるが、戦後の混乱と共に1953年に養子縁組でアメリカヘ連れて行かれ、名前はバーバラに改名された。本作のタイトルである『Yokosuka1953』の“1953”は、洋子が強制的に“アメリカ人”バーバラになった年なのだ。木川剛志さんはクラウドファンディングでバーバラさんを日本へ招き、信子さんの軌跡をたどってゆく。このときはまだ、この先どんな過去が待ち構えているのかを知らずに――。
全体を見て思うのは、語り継ぎたくない地域の歴史は、いとも簡単に“公然の秘密”にされてしまうんだということ。戦後の横須賀では町にパンパンが立っていた。孤児院も多かった。差別もひどかった。家を壊したら赤ん坊の骨がたくさん出てきた。戦時中なら当たり前だったことは、戦後、人々が口にしなくなる。閉ざされた口は再び開くことはなく、歴史は静かに消えてゆく。過去を丁寧に掘り起こしてゆく課程で、信子さんは当時、幼い洋子(バーバラ)さんを育てるために身体を売っていたことを知る。知った彼女は言う。「それは母が私を養うためにしたこと。悪いことであっても隠す必要はない。人に言うことが大切。口に出さないと癒やされない。より良い人生を歩むために母は私に生きるチャンスを与えたのです」と。
幼女で海を渡り、66年を経て老女になって帰ってきたバーバラ=洋子さん。彼女の壮絶な生い立ちは戦争がもたらしたひとつの悲劇ではあるかもしれない。けれど本来消えてしまうはずの証言が記録され、映画となり、観客は知らなかったことを知ることで国を超えてお互いを理解する。それはやがて和解の糸口になるだろうという希望。『Yokosuka1953』は命を感じる力強い作品。人が生きること、命が繋がっていくことの素晴らしさを全身で浴びる躍動がありました。
上田の自主映画祭はフィクション、ノンフィクション、アニメなどジャンル問わず受け付けていますが、総数としては劇映画が大半を占めます。けれど『Yokosuka1953』は、1本の映画として、すべてのジャンルを飛び越えた、過去を掘り未来に渡す「命の繋がり」を描いた見事な作品です。かつて『ミリキタニの猫』(06)というドキュメンタリーがありましたが、人生には予想もしない、どうにも引き寄せられ導かれてしまう縁を持つ人がいます。木川剛志監督もまさにそのおひとり。縁のバトンを受け取ってくれて本当に良かった。“その場”に居合わせて記録して映画にして下さって、本当にありがとうございますという気持ちです。バーバラさんと共に木川信子さんを探す、まったく先の読めない106分間の旅を、ひとりでも多くの方に観て戴きたい、観た人と共有したい。その想いに突き動かされての大林千茱萸賞となりました。映画を観終えたいま、もし「木川信子を知っていますか?」と聞かれたら、私は「えぇ、よく知っていますとも!」と、胸を張り答えることでしょう。それが映画の力です。『Yokosuka1953』制作に関わられた木川剛志監督はじめ、信子さん、洋子さん、ご家族――すべての皆さまに感謝を。おめでとうございます!(大林千茱萸)
柘植靖司賞「アクト」
本来、私はドキュメンタリー映画というものにあまり興味はなく、制作に関わったことも、制作しようと考えたこともありませんでした。
練りに練った脚本、入念な制作準備、そして撮影現場でのスタッフ、キャストの共同作業による悪銭苦闘…許される限り、何度も何度も納得が行くまでやり直す。それが私にとっての映画制作でしたから、ぶっつけ本番のドキュメンタリー撮影というものに、ある種の怖さを感じていました。
人は誰しも日常の生活で意識、無意識の内に、自分というものを演じていると思います。職場での自分、家族の中での自分、友だちや恋人の前にいる自分。みんな、その時々の自分を演じています。ただ、誰も、自分にカメラが向いているとか、記録されているとか、それを観る観客がいるとは思っていません。しかし、この作品の主人公はその日常の生活でカメラが回っていることを知っています。しかも、主人公はプロの役者であり、このドキュメンタリーの監督でもある。作品を拝見していて不思議な感覚がありました。
母親としての田中夢さん、妻としての田中夢さん、学生であり俳優である田中夢さん…。どの田中夢さんにも、脚本があるわけでもなく、ぶっつけ本番の日常を必死で生きている田中夢さんだと思います。しかし、それを撮影している田中夢さんがいる。被写体になっていることを知っている田中夢さんがいる。
ある著名な監督が、『優れたドキュメンタリーはフィクションに近づき、優れたフィクションはドキュメンタリーに近づく』と言っていますが、この作品は、まさにドキュメンタリーとフィクションの狭間にあるのでは、という面白さを感じました。
正直に言いますと、「こういう表現方法があったか、『アクト』かあ、…してやられたな」と思った次第です。これがこの作品を『柘植賞』に選ばせて頂いた最大の理由です。
生活していくことも、夫婦関係も、子供を育てることも、大変だよな、と共感しながら、少しだけ残念だなと思ったのは、田中夢という人がこの生き方を選択し、生きている日々の喜びのシーンがもう少しあっていいのでは、と思いました。そうした瞬間の田中夢さんが描かれることで、もっと田中夢さんの生きざまが観客に近づくのでは、と思いました。
最後に、この映画祭に俳優賞があるのならば、息子さんのちがやクンは間違いなく主演男優賞です。
田中夢さんの今後のご活躍を楽しみにしています。(柘植靖司)
古厩智之賞「バンド」
バンドのボーカルをやめてボクシングに傾倒して行く彼がいい。自身のなさと凶暴さがないまぜになった不穏さと優しさのある目。
ボーカルに置き去りにされるギターの彼もいい。マッシュルームヘアの下から覗く目がいい。スネているのに実は誰より誇り高い…。青春の情けなさや後ろ向きさを堂々と出してる丸まった背中がいい。
彼らのあいだで立ち尽くすドラムの女の子がいい。目は両者のあいだを揺れて、、でもまったく媚びない。けどつっぱらない自然な空気。
そんな3人の青春は、3人だけのものであって。それを安易に肯定しようとする奴は、こちらを侵す奴なのだ。青春は3人のあいだでだけ輝いていればいい。
青春の空気を、実感とともに、しかし距離を持ったクールな「映画の目」で掴み取っている。感動しました。(古厩智之)
実行委員会特別賞「Yokosuka1953」
最初の予期せぬ出来事は一通のFacebookメッセージ、その瞬間が次の出来事を呼び、その出来事が更に次の瞬間を生む、幾つもの瞬間はカメラとマイクにより確実に記録され、積み重なる。更にそれら一つ一つの瞬間を再構築することで魂が吹き込まれ、今まで出会うことのなかった新しい世界を提示してくれる作品だ。
特に映画「Yokosuka1953」の場合、素材となるそれぞれの映像(記録)の内容が極端に違う。
例えばそれは、戦争と平和だったり、日本とアメリカだったり、現在と過去だったり、男と女だったり、個人と組織(社会)だったり、ほとんどが180度違う内容(映像)の積み合わせだが、それが故に言葉では創り出すことができない新しい世界(価値観)の表現に成功している。
「映像は記録だが、映画は記憶だ」大林監督お話の一節ですが、まさにこの作品は記録ではなく記憶になっている。(実行委員長 山崎憲一)